
株式会社shizai 執行役員 営業/マーケティング統括 小田 高弘氏
同じ商品でも「届いた瞬間」の印象が全然違う。——そんな経験はありませんか?
実はその差を生んでいるのは、商品そのものではなく届け方、物流や資材の違いにあるのです。
Eコマースにおいて物流や資材は不可欠な要素であるにもかかわらず、多くの事業者にとっては依然として、できる限り安く抑えるべき“コスト”とされてきました。
しかし今、「資材=コスト」という常識を覆し、ブランドにとって、顧客との最初の接点である資材を“顧客体験の主役”に変えるサポートをしている企業があります。
本記事では、資材を単なる梱包材ではなく、「コミュニケーションツール」へと再定義した事例とともに紹介します。
資材の価格差、なぜ生まれる?今さら聞けない資材調達のリアル

Eコマース業界が伸びていく中で、「箱」をはじめとする資材の重要性は、ますます高まっているように思います。でも実際には、まだ“ただの梱包材”として扱われていることも多いですよね。
御社では、物流効率だけでなくブランディングの視点からもパッケージを進化させているのが印象的です。まずは、その着眼点に至った背景から伺えますか?

僕たちが事業を始めた頃は、Eコマース市場がこれからどんどん伸びていくだろうというタイミングでした。
Eコマースは、やることがほんとにたくさんあるじゃないですか。マーケティング、商品開発、接客、ブランディング……。しかし当時、「資材」や「サプライチェーン」など“裏側”に詳しい人が、フロント業務に携わる方に比べると相対的に少なかったんです。

わかります。華やかなフロントの話はよく聞くけれど、梱包や出荷の話は、あまり表に出てこないですよね。

そうなんです。しかし実際にD2Cをやられている方々と話してみると、「どうやってパッケージを選べばいいの?」「どこに頼めばいいの?」という、基本的なところでみんな困ってることに気づいたんです。

そもそも「資材市場」を、どう定義されてるんですか?

めちゃくちゃ広いですよ(笑)一説では、「包むものすべて」を含めると7〜8兆円の市場規模と言われています。そこに印刷包材市場、みたいな切り口いれるかどうかでどうかでも、2〜3兆円の市場規模で変動するので、明確に把握はできていないです。

そんなに大きいんですね……!

私たちが捉えているのは、Eコマース、つまりオンラインで商品を届けるときに使う資材——外箱から中の仕切り、緩衝材まで、すべてを含めた「Eコマースビジネスに使う資材」と少し絞った範囲です。


なるほど。物流まわりの重要性は理解してるつもりでも、いざ始めるとなると「何をどこまで頼んでいいのか」迷ってしまいますよね。

ですよね。パッケージのコスト構造もわかりづらいし、工場ごとの得意分野も見えづらいです。
同じ仕様のパッケージを複数の工場に見積もってもらったんですが、出てくる金額がバラバラで私たちも、「えっ、なんでこんなに違うの?」という状態からのスタートでした。そこから徐々に情報を紐解いて、「どんな製品が、どの工場に向いているのか」という知見を積み重ねていきました。
だから、Shizaiの事業も最初はとてもシンプルで「同じものを、得意な工場で、より安く提供する」ところから始まっています。


実際に、お客さまからの相談にはどう応えているんですか?

お客様の要件や実現したいことをお聞きした上で、まず頭の中では「どこの工場に相談するべきか?」「どんな組み合わせ、スキームが一番効率的か?」を考えます。
その上で、過去の事例や各工場の得意分野を踏まえながら、具体的な提案を組み立てていくイメージです。
最近では、資材工場だけでなく、倉庫や配送業者さんとのネットワークも広がってきました。そのおかげで、資材の提供にとどまらず、最適な倉庫の紹介など、サプライチェーン全体の最適化まで提案できるようになってきています。
サプライチェーンは、営業やマーケティングと比べると経営判断としてもどうしても投資を後回しにされやすい側面を感じます。私自身、前職がメーカーだったこともあり、その事情は感覚的にすごく理解できるんです。
だからこそ、アナログなまま“残されている領域”に、介在できる価値があると思ってます。

資材は単なる箱ではなく、倉庫の作業効率や製造コスト、物流の最適化まで関わってくるものですよね。関係者も多く、設計にはかなり気を使う部分だと感じます。

そうなんですよ。やることも多いだけではなく、「それって売上につながるの?」と、不安に思う方も結構多くて。実際、事業者さんと話してても、そこがネックになることはよくあります。
「資材=コスト」はもう古い。「ただの箱」から「ブランドのタッチポイント」へ

それにしても、物流業界はまだまだアナログな部分が多いんですね…!

そうですね。創業当初は、工場とのネットワークを活かした「コスト面の差別化」がメインでした。
事実、2010年代後半までは段ボールなどの梱包資材はあくまで「安全に運ぶためのもの」でした。しかし2020年以降、コロナの影響でガラッと変わり、クライアントから“プラスアルファ”を求められるようになってきた実感があります。

“プラスアルファ”というと?

もともとあったAmazonや楽天などの大手のECモールに加えて、自社Eコマースでの販売も一般的になりました。更に、ここ10年弱でD2Cブランディングが一気に広まりましたよね。
D2Cのクライアントさんの多くが、インターネット上でブランドの世界観をしっかり作っています。それにもかかわらず、茶色い段ボールに雑な緩衝材にくるまれた商品が届いたら、がっかりしますよね。
そこに気づき始めたブランドが、「リアルな接点であるパッケージにこそ、もっと投資すべきだ」と考えるようになった。だから私たちも「ただの箱」から「ブランドのタッチポイント」へと、パッケージの役割を再定義しています。


最初からパッケージにイノベーションを起こそうとしていたわけではなく、現場の課題と向き合う中で進化していったわけですね。

そうですね。現在は、お客さまの半分はD2Cのブランドさんです。そういう方々と「どんな箱にする?」と話をしていると、皆さん“顧客体験”を起点として考えていらっしゃいます。

実際、どんな相談が来るんですか?

たとえば、おもちゃのサブスクをやっている企業さんから以下のようなオーダーを頂きました。
子どもが箱を開ける瞬間にワクワクできるようなデザインにしたい、しかし輸送にも耐えられる資材でなければいけない
そんな要望に応えるために、僕たちもデザインや設計の段階から一緒に考えるようになったんです。このような事例が増えていく中で、「コストを抑える」だけじゃなくて、「ブランドを伝える」ためのパッケージという考え方が根づいてきたように思います。

ただ、「ブランドを伝えるためのパッケージ」と言っても、やれることが多すぎて、どこから手をつけていくべきか迷ってしまいそうですね。

まさにそこです。やりたいことがたくさんある分、コストや工数を見積もって、優先順位をつけて進めていく必要があります。
「目に見える課題」と、「本質的な課題」が違うことも往々にしてあるので。

そのあたり、どんなバランス感覚で提案されてるんですか?

お客さんが「一番の課題」だと思ってることと、私たちが「本当の課題」だと思ってることは、ズレることがよくあるんです。しかし、基本はちゃんと寄り添うことを大事にしてます。そのうえで、課題解決のパターンを複数提案します。
「この方法で解決できますよ」と伝えつつ、「実は、もうひとつ別のアプローチもありますよ」と提案します。それを聞いて「たしかにそうだね」となれば進められるし、「今は上司の意向でこっちから進めたい」ということもあります。
だからこそ復数の選択肢を持ってもらうことが大事で、本質的な課題を見極めたうえで、どのように優先順位を置くかを、一緒に考えていくスタンスです。

箱で変える体験設計。ブランドを支える課題解決型パッケージの力

物流現場では、流通加工や梱包・発送のオペレーションを変えるだけでもかなり大きなプロジェクトになりそうです。だからこそ、気軽に「とりあえずやってみよう」とはなりにくいですよね。調整が難しい点も多いかと思います。

小田さん
まさにその通りです。物流現場の実情としては、限られた人数で何とか業務を回しているケースが多く、資材の種類が増えたり、組み立て作業に手間がかかるような提案は受け入れられにくいのが現実です。
ただ、私たちが資材提供者として一歩先回りし、たとえば「この資材を使えば、1個あたりの組み立て時間が●秒ほど短縮できます」や「テープによる封緘作業が不要になります」といった形で、物流現場の目線に立って具体的に説明すると、「それは助かる!」と前向きに受け入れてもらえることも多いんです。

御社は、細やかなニーズや頻繁な仕様変更にも柔軟に対応されていますね。しかし、ここまで一つひとつのブランドに合わせてカスタマイズするのは大変では?

たしかに、対応の手間だけを見れば効率的とは言えないかもしれません。ですが、資材に求められる役割や機能が多様化し、提案の内容もより細分化されてきている今、私たちはその変化に応えていくことが重要だと考えています。
資材市場全体から見れば、私たちが向き合っている領域は相対的に狭いかもしれません。しかし、その中には深いニーズや多様な資材の可能性が広がっていて、私たちが価値を提供できる余地も大きい。だからこそ、しっかりダイブしていく意味があると感じています。

カスタマイズ対応が強みとのことですが、具体的にどのようなアプローチをされているんでしょうか?

まだ「なんでも応えられます!」という状態ではないのですが、お客さんから「こういう人に届けたい」「こんな体験をしてほしい」といったカスタマージャーニーや想いを共有してもらえると、そこから大きなヒントが得られます。
その結果、私たちの持っている提案の引き出しやパターンと掛け合わせることで、新しい提案が生まれることもあるんです。


なるほど。そのカスタマージャーニーから逆算して形にしていくんですね。印象的だった事例はありますか?

たとえば、ある大手メーカーさんとご一緒したときのことです。「健康管理のプロダクトを、日常の中で無理なく取り入れてもらいたい」という要望をいただきました。
そのときに出てきたのが、「どこに置けば“自然に”使ってもらえるんだろう?」という話です。そこで私たちが提案したのが、「トイレに置いてはどうか?」というアイデアでした。やはり“日々のルーティンに溶け込む”ということがすごく大事だと思い提案しました。
しかし、トイレはスペースが限られているので、そこに置けるような形にする必要がありました。そこで、薄くてコンパクトな段ボールにして、しかもスタンド型にして立てられるように設計したんです。
こういった細かい工夫を重ねながら、使う人の生活導線に自然と寄り添える形を考えていくと、結果的にユーザーにも使いやすくなって、喜んでもらえるんですよね。

それはまさに一緒に「つくる」感覚ですね。

そうなんです。お客さまとの対話の中から「ここが肝になりそうだな」というポイントを抽出して、それをベースに工場ネットワークといっしょに相談しながら進めていきます。
「こんなことやりたいけど、御社でできそうですか?」と聞くと、意外と「やれるかも」と返ってくることも多くて。
ブランドの持っている「やりたいこと」と、現場の「できること」の掛け算から、自然といい提案が生まれるんですよ。

とはいえ、ブランドごとに違うニーズへの対応は、試行錯誤の連続なのでは?

その通りです。「前例があるから大丈夫」という世界ではないので、「やりたいこと」と「できること」のギャップをどう埋めるかが、最も時間をかけるところですね。

お客さんによっては、「そもそも何ができるのか分からない」状態からスタートすることも?

はい、パッケージの知識がないお客さんも多いので、最初はご予算と照らし合わせながら「このくらいまでならできますよ」と、少しずつ選択肢を整理していく感じですね。

そうして話を聞いていると、「それ、もうイノベーションじゃない?」というケースも多そうです。

いや、本当にそうなんですよ(笑)。やりたいことを一緒に探しながら、一歩ずつ形にしていく。その積み重ねが、私たちの価値だと思っています。

“ただのパッケージ”で終わらせない。ブランド・倉庫・工場・Shizaiがつながる「四方よし」の共創

そこでもやはり“三方よし”のバランスを意識されてる?

そうですね、私たちもその意識を強く持っています。
「サプライチェーンの最適化」という言葉をよく使うんですが、実は“三方よし”どころか“四方よし”を目指してるんです。

四方よし!?

はい。たとえばブランドの皆さんは「事業を伸ばす」ために、色んな新商品やプロモーションにチャレンジしたいと思われるのが当然だと思います。
ただし、倉庫の視点から見ると、人員や工数に限りがあるため、「どんな要望にも応えられる」というわけにはいかない現実もあります。また、工場にとっては、得意で適正な利益が見込める商品ではなく、「一応つくれるけれど、ほとんど利益が出ないものばかりを納品している」といった状況に陥ることもあります。
こうした三者それぞれの”ペイン”を丁寧にすくい上げながら、ブランドの「やりたいこと」と、現場の「無理なくできること」の交差点を見出していく。そこで、私たちが最適な工場の選定や、物流負荷を踏まえた設計を通じて、無理なく、かつそれぞれが本来の力を発揮できる形を整えていく。
結果として、ブランド・倉庫・工場・shizai——すべての関係者が共存できる仕組みが生まれていきます。

なるほど……たしかに、選び方の情報が偏っているだけで、本当はうまくいく仕組みがあるんですね。

そうなんです。たとえば、「この工場さんが得意な分野だよ」とか「この倉庫さんが使いやすいよ」という情報は、なかなか表に出てこない。つまり“情報の非対称性”が大きいんですよ。
だからこそ、私たちがその“いい組み合わせ”を見える化してあげることで、関わる全員が幸せになれる。結果として、三方よしから、四方よしの世界が実現できるのではないかと思います。


クライアントの課題を起点に、どのように「四方良し」の仕組みを実現されたのか、具体的な事例があれば教えてください。

あるブランドさんの事業が急成長していて、私たちとしてもそれは本当に嬉しいことだったんです。
しかし一方で、出荷を担う3PL(サードパーティロジスティクス)※のキャパシティが限界を迎えてしまったんです。「出荷が間に合わない=売上のチャンスを逃している」という状況が課題でした。
※3PLとは…Third Party Logisticsの略で、荷主企業の物流業務を代行する第三者物流サービスを指す


なるほど。それは物流が完全にボトルネックになってしまっていたと。

はい。しかも原因は人手やシステムの問題ではなく、「梱包作業そのものの手間」ということがわかりました。
ミカン箱型の段ボールを一つひとつ手で組み立てて、テープで封をして…という作業が非常に重たく、1日数千件レベルになるとどうしても限界がきてしまっていました。そこで、「そもそも資材を見直してみよう」という話になったんです。

そこからどのように改善されていったのでしょうか?

ブランドさんと3PL、そして私たちの三者で「どうすれば出荷がもっとスムーズになるか?」を何度も話し合いました。最終的に「箱の構造そのものを変えよう」と提案したんです。
具体的には、まず底面を「ワンタッチ底」に変更しました。箱を立ち上げると自動で底が閉じるので、組み立て時間はグッと短くなりました。


ワンタッチ底はよくある形ですよね。なぜ、最初から採用されていなかったんですか?

実は、ミカン箱が得意なメーカーさんのなかには、ワンタッチ底に対応するラインを持っていない場合もあります。また、得意な製造ラインを活かしたほうが、効率的に生産できることもあるため、提案が難しいケースもあるんです。
そこで私たちが間に入り、ワンタッチ底の加工を得意とする工場と連携することで、倉庫と発注側の双方にとって負担の少ないかたちに組み替えることができました。

天面の構造にも工夫があるとか。

そうなんです。もともとはテープで封をしていたんですが、工場の作業としても手間であるだけではなく、ユーザーにとっても開封時の体験としてもあまり良くありませんでした。
そこで、10回以上サンプルを作り、最終的に「サイド差し込み+送り状封緘」の構造にしました。
これなら配送中に開いてしまう心配もなく、お客さまもストレスなく開けられる”開ける体験”を損なわない設計を意識しました。
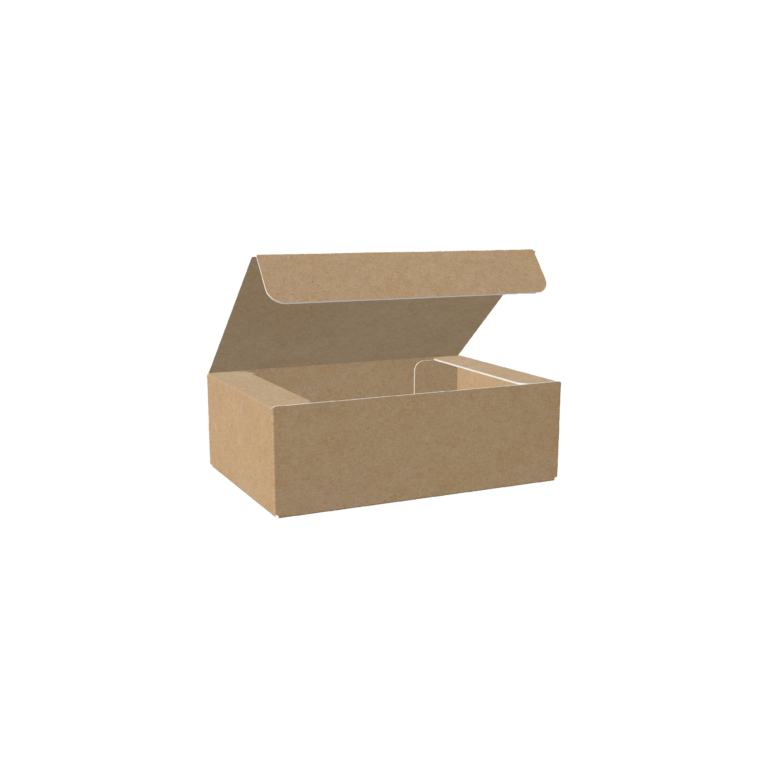

それだけ手の込んだ資材だと、コストが気になるところですが……

実はそこまで上がっていないんです。たしかに資材単価は少し上がったんですけど、組み立てや封緘の工数が削減できたことで、トータルコストはむしろ下がったとも言えます。

なるほど。その後のブランドさんの反応はいかがでしたか?

無事に出荷体制が整い、売上も再び成長軌道に乗りました。物流資材は、ただの「箱」ではないんですよね。ブランドの世界観を届ける“最後のメッセンジャー”ということが伝わったと思います。

なんか今、めちゃくちゃ腑に落ちました。全ては「知らなかっただけ」だったんですね。

そう、それに尽きます(笑)。みんな「知らなかっただけ」なんですよ。だから、私たちはそれをまとめて、プラットフォームとして整理している感じです。
Eコマースの世界は、ここ数年ですごく広がりましたが、国内レベルでもまだ発展途上で、世界と比べると市場シェアはまだまだ小さいです。だからこそ、知られていないことが多い。そこが本質的な課題だと考えています。
 編集後記
編集後記今回のお話で特に印象に残ったのは、「三方よし」ではなく「四方よし」という考え方です。ブランド、工場、倉庫、shizai——それぞれの役割を最適化し、全体を俯瞰して“見える化”することが、理想的な関係を築くためには重要だと感じました。これからのものづくりや流通の現場では、この視点が求められるのでしょう。
特に資材に色んな役割を求めるEコマース主体で販売している事業者にとっては、私たちのネットワークが「助け舟」になれる可能性があるという言葉に、未来の展望が感じられました。
箱は単なる「入れ物」ではなく、ブランド価値や体験を伝える「メディア」として捉えることで、箱のイノベーションは、デザインや素材の変更にとどまらず、ブランド体験の向上に直結する大きな一歩として、その役割をますます拡大していくのではないでしょうか。
文 :杉山 美和
写真:関 大二郎

